かつて、筑豊本線・中間〜筑前植木間は3線区間だった。さらに折尾〜中間間においては複々線、香月線も新手〜中間間は3線だった。急増する石炭輸送を増強していった結果であり、複線でもさばけない程の列車があったことに驚くばかりである。ちなみに筑豊本線で初めて複線化されたのは、1893年(M26.12.20)/底井野〜植木間だった。底井野とは、現在の筑前垣生駅と遠賀川橋りょうの間にあった信号所。これについてはまた後日。
時が経ち、多くの石炭列車が行き来した線路には、銀色の電車が颯爽と通過していく。その足下、上下線の真ん中には3線時代の遺構が今も残っている。では、その遺構へ行こう!
まずは筑前垣生〜鞍手間の遺構から。
●尾尻架道橋

手前から上り・撤去線・下り。3番目に増線した部分はコンクリート製になっている。
煉瓦橋台を見てみると、自然風化のせいかワザとなのか分からないが、
ポリクロミーっぽくなっているのが面白い。
↓筑前垣生側

↓鞍手側

時が経ち、多くの石炭列車が行き来した線路には、銀色の電車が颯爽と通過していく。その足下、上下線の真ん中には3線時代の遺構が今も残っている。では、その遺構へ行こう!
まずは筑前垣生〜鞍手間の遺構から。
●尾尻架道橋

手前から上り・撤去線・下り。3番目に増線した部分はコンクリート製になっている。
煉瓦橋台を見てみると、自然風化のせいかワザとなのか分からないが、
ポリクロミーっぽくなっているのが面白い。
↓筑前垣生側

↓鞍手側

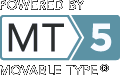
コメントする